最終仕入原価法について
商品Aを単価10円、20円、30円と3回に分けて各1つずつ仕入れたとします。
そしてこの仕入れた商品全てが売れ残ったとします。 この場合、仕訳上、帳簿には仕入れ時に勘定科目「仕入」として10円、20円、30円を仕分けし、仕入れ合計60円となっていると思います。
しかし、最終仕入原価法を採用した場合、同じ商品を最後に仕入れた単価で計算することになり、棚卸時に90円(30円×3回仕入れたことになる)となり、実際仕入れに使用した金額が60円であるのに棚卸時に90円と資産(商品)が+30円増えることになります。また、逆に30円→20円→10円の順に仕入れた場合、これが逆に実際仕入金額60円に対して棚卸時の売れ残り商品の資産評価額は30円となり、実際に仕入れた金額より-30円となります。
つまり、最終仕入原価法を使用した場合、
最後に仕入れた金額が実際の金額より高いと棚卸時に資産が増えてしまい逆に最後に仕入れた金額が低いと棚卸時に資産が減る計算になってしまいます。
このあたりがよくわからず解説していただきたく思います。
仕入単価ごとに計算すべきで無い理由も教えて頂けたら幸いです。
- 投稿日:2025/03/25
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士をお探しの方におすすめ

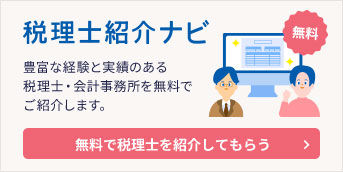
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所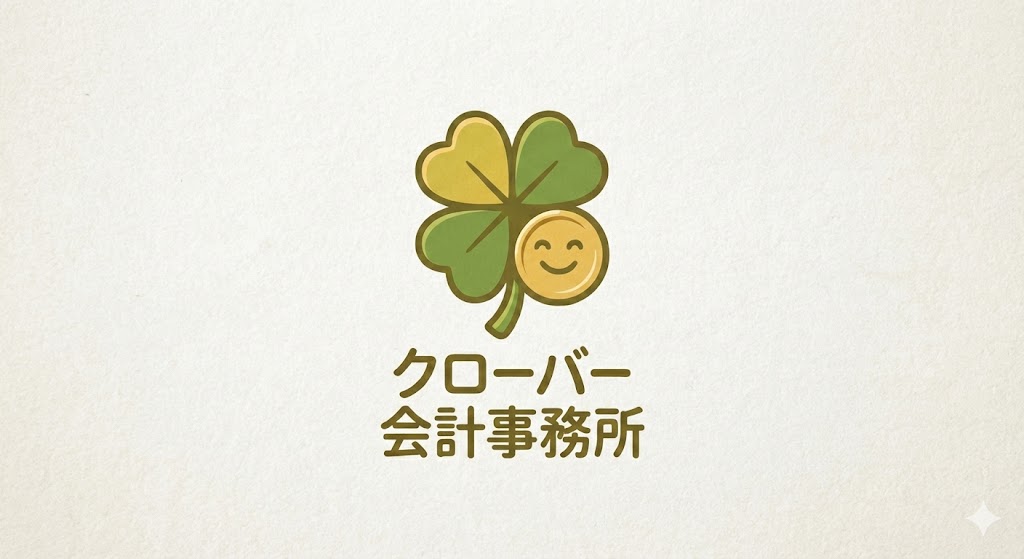
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する


